広告がまた炎上している。そして、サントリー「頂」の一件を見ていて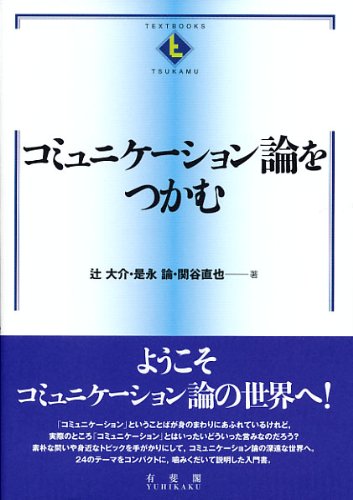 思ったんだけど、もはや「文脈(context)」ということを広告クリエイターがあまり考えなくなったんだろうな。
思ったんだけど、もはや「文脈(context)」ということを広告クリエイターがあまり考えなくなったんだろうな。
いや、かつては打ち合わせで「この企画の文脈は~」とか、そんな話をしていたわけじゃない。表現を考えたときに、「誰がどんな時にどう感じるか」をいうことをどこか意識しながら、「これはやばいんじゃない」とか話しながら企画を固めていたはずだ。
いや、別に文脈っていうのはそんな難しいことじゃなくて、講義や研修などではこんなことを話している。
いきなり、一人の学生や受講生に向かってこう言う。
「バカ」
で、「ごめん、いまイラッとした?」というと、大概の人は頷く。中には「相当むかついた」という人もいる。
そうだよね。じゃあ、こういう会話はどう?
「あ、いっけねえ~」
「どうした?」
「この暑いのに、ホットの缶コーヒーのボタン押しちゃったよ」
「バカだね~」
ほら、別にイラッとしないでしょ。同じ「バカ」でも文脈によって感じ方は違うんだよ。ただし、それが微妙なところもあるんだな。 >> 問題になる広告は、「文脈」を忘れてる。の続きを読む
 この本のタイトルを見た時に既視感を覚えた人はいるんじゃないだろうか。そう、佐野眞一氏の『誰が「本」を殺すのか』という本が話題になったことがある。
この本のタイトルを見た時に既視感を覚えた人はいるんじゃないだろうか。そう、佐野眞一氏の『誰が「本」を殺すのか』という本が話題になったことがある。
作り手と売り手、そしてチャネルなど業界関係者の意識変化がなかなか進まないままに、気がついたら風景が一変していた――そういうところは、出版とアパレルの両業界に類似点はあるかもしれない。
しかし、「誰が」という問いに対して犯人を特定することは難しい。何に近いかというと、『オリエント急行の殺人』のようなところだろうか。もっとも、服そのものに罪があるわけじゃないのだけれども。
この本の中に書かれていることは、まったくその通りだと思う。また、終章に描かれている、新たなチャレンジャーの方向性も納得できる。しかし、それ以前に市場が一段と縮小していくのは避けられないと思う。
それは、景気とか少子高齢化とは全く別の動きなのではないだろうか。カンタンに言うと、「自己表現する」あるいは、「顕示欲求を満たす」手段として服の役割が終わりつつあるんじゃないか。
少なくても、日本ではそうだと思うし、先進国の状況は似ているように感じている。
「服を着る」ということ自体は、人が生きていく上で「道具」として必要なものだった。それが、どのようになったかは、「ご覧の通り」としか言いようがない。
そして、衣服はある時代から社会学や哲学の研究対象となっていく。「モード」を語ることは、人のあり方を語ることのような時代もあった。というか、そういう人もたくさんいて、普通に暮らしてセールを追っかけるくらいの人たちも、彼らの分析対象になっていた。
それほど、人々はファッションにおカネを使っていた。 >> 【書評】『誰がアパレルを殺すのか』~”貴族の模倣”が終わる時。の続きを読む
 先日、自宅の呼び鈴が鳴った。十中八九は届け物だし、心当たりもあったわけでそのつもりでボタンを押す。
先日、自宅の呼び鈴が鳴った。十中八九は届け物だし、心当たりもあったわけでそのつもりでボタンを押す。
「アマゾンです」
そう。たしかにアマゾンで頼んでいたのだけれど、違和感がある。そうか、今までだったら「ヤマト運輸です」だったのだ。
そして、「アマゾンさん」は紺色の服を着たどこかの配送業の方だった。その後も、同じ方がやって来る。でも、僕にとっては、「またアマゾンを届けてくれた誰か」である。
一方で、ヤマトの場合は「誰が届けてくれるか」がわかっていた。家に一番来るヤマトの人はKさんで、最近は女性のNさんもいる。その前はMさんやTさんだった。自宅で仕事をしていることが多いので、結構顔見知りにもなる。
つまり、僕にとって「アマゾン」という“便利な”ブランドは、ヤマト運輸の彼らによって成り立っていたのだ。「アマゾンという何だかすごいシステム」は遠くにあるが、それを「現実化している人」として、ヤマト運輸のドライバーとの間には、ある種のエモーショナルな絆が成立していたことを改めて感じだ。
そういえば送り主のトラブルで配達が遅れた時なんか「すいません」「別にいいですよ」とかやり取りしていて、単に配送者と客という関係じゃなかったんだな。
一方で、「アマゾンです」と言ってくる彼は誰なんだろう?
運輸会社も、ましてや名前もわからない。今度不在者伝票が入っていたら、確かめられるのかもしれないが、あの匿名の「アマゾンさん」は何か引っかかる。
SF的に考えると、アマゾンというアンドロイドだったりして。というか、将来はそうなるんだろうな。
とはいえ、そんな妙な喪失感を味わうのもいっときのことだろう。物流の合理化はさらに進まざるを得ないだろうし、「人と人の接点」というのもなくなってみれば、意外にもすぐ慣れる。
そういえば服を買う時も、知っている店員のいる店に行かないで、ネットで済ましたりしてるよな、と思っていたらこんな本を知った。
『宅配がなくなる日』というタイトルだけど、宅配の話に続いて三越伊勢丹の問題が論じられている。一見すると関係なさそうなこの2つのテーマだけれど、サブタイトルの「同時性解消」という言葉がカギとなっているのだ。
電話とメールなどが典型だが、「同時に複数の人を拘束する」ということが解消されていく中で、どのようなビジネスの機会が生まれるかを論じた一冊だ。著者はフロンティア・マネジメントの松岡真宏さんと山手剛人さんである。
既に「そうだよな」と思っていたこともあるけれど、もちろん気づかな点もある。そして、実はこの「同時性解消」についてきちんと論じた本は今までなかったんじゃないか。そこを起点にして将来を考えるというのも、おもしろい。
人口減少社会における、新しい切り口の提言もあって、これからのマーケティングにおける1つの視点としても大切な切り口の一冊だと思う。
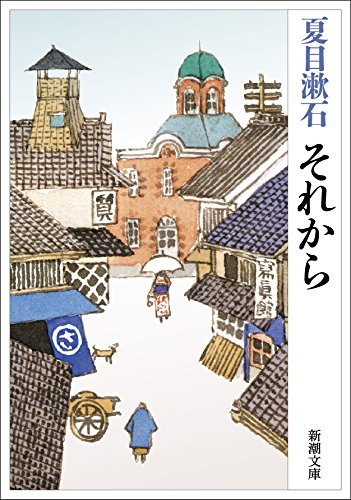 先日読んだジェフリー・ディヴァーの『扇動者』(文藝春秋)は、内容も面白かったのだけど、細かい描写がいかにも現代だった。警察関係者が捜査会議をしている時に、勝手にスマートフォンをいじっている場面が結構出てくる。
先日読んだジェフリー・ディヴァーの『扇動者』(文藝春秋)は、内容も面白かったのだけど、細かい描写がいかにも現代だった。警察関係者が捜査会議をしている時に、勝手にスマートフォンをいじっている場面が結構出てくる。
それが、場の心理を絶妙に表現しつつ、後で考えてみるとちょっとした伏線にもなっているのだが、まあ世界のどこでもスマートフォンはなかなか手放せないだろう。
この小説の場合はスマートフォンの描写がリアリティを高めるのに効果的なのだけれど、現代の人間をそのまんま描写すると、身も蓋もなくなる。ハードボイルドの小説で、探偵がバーカウンターでスマートフォンをいじっているわけにはいかない。
また、古典小説に無理矢理スマートフォンを登場させると、どうなるか。
「クトゥーゾフはくたびれた目でデニーソフをながめはじめ、腹立たしそうな身振りでスマートフォンを見ると、彼の言葉を繰り返した」
「彼が見ていた家から、本当に、デニーソフが話しているあいだに、スマートフォンを片手に将軍が姿を現した」 >> 漱石の小説に無理矢理「スマホ」を登場させてみる。の続きを読む
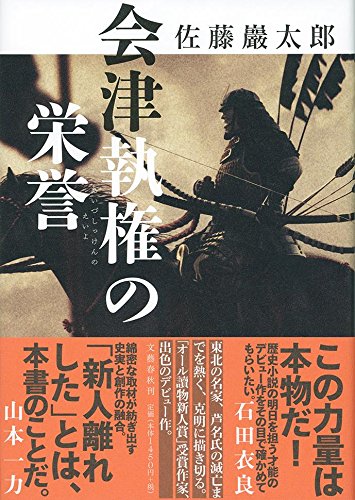 歴史小説は、嫌いではない。というか、特定ジャンルの小説ばかり読むわけでもないので「まあ好きなものの1つ」というくらいだろうか。このカテゴリーのおもしろいところは、結構歳を重ねてからデビューされる人も多いことだと思う。
歴史小説は、嫌いではない。というか、特定ジャンルの小説ばかり読むわけでもないので「まあ好きなものの1つ」というくらいだろうか。このカテゴリーのおもしろいところは、結構歳を重ねてからデビューされる人も多いことだと思う。
『会津執権の栄誉』(文藝春秋)を描かれた佐藤巖太郎氏も、1962年生まれで2011年にオール読物新人賞を受賞している。加藤廣が連載していた『信長の棺』を発刊したのは、なんと75歳だ。
新聞記者だった司馬遼太郎がデビューしたのは36歳のことだが、72で没しているので後半生のみで、あれだけの作品を書いたことになる。若くして書いていたら、と思わずにいられないが、やはり歴史小説を書くには「絶対年齢」が影響するところはあるのだろう。
ことに生死が紙一重の世を生きていた者たちのリアリティは、それなりに人生経験を重ねた者でないと表現が難しいのだろうか。
いや、年寄りくさい話になったけれど、この小説は構成が緻密で人物もクッキリ描かれていて、かつちょっとしたミステリアスな趣向もある。 >> まだ戦国には鮮度がある~『会津執権の栄誉』と『駒姫』【書評】の続きを読む








