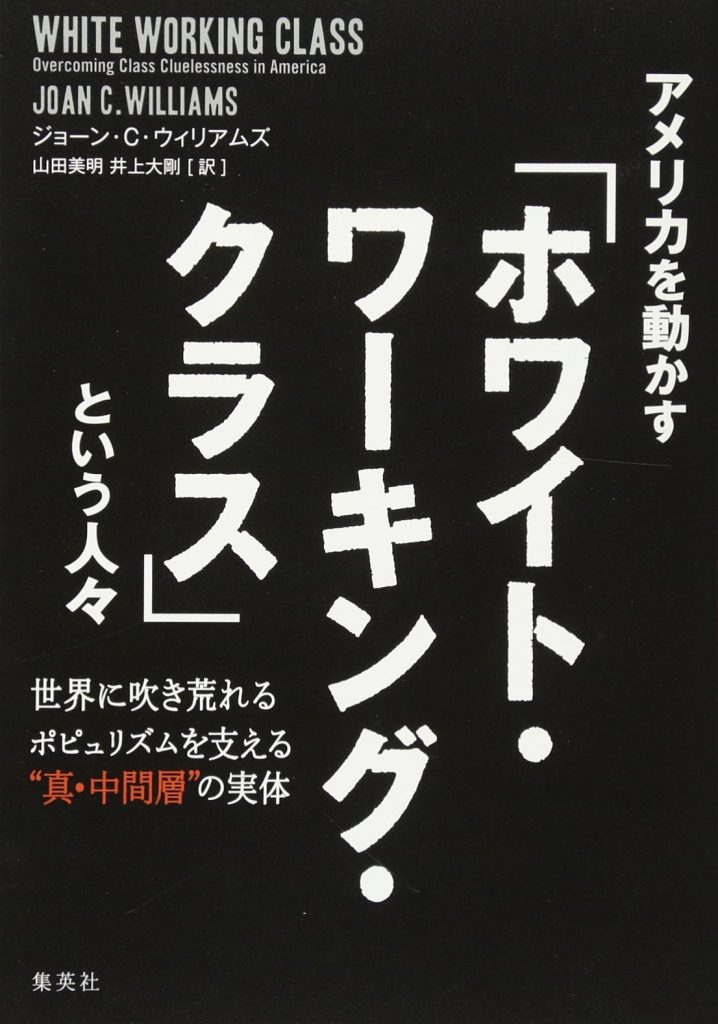 ジョーン・C・ウィリアムズ著/山田美明・井上大剛(訳)『アメリカを動かす「ホワイト・ワーきんぐ・クラス」という人々』(集英社)
ジョーン・C・ウィリアムズ著/山田美明・井上大剛(訳)『アメリカを動かす「ホワイト・ワーきんぐ・クラス」という人々』(集英社)
考えてみれば「あの」大統領選挙から、ちょうど1年になる。
トランプの選出に驚いたメディアは、その「支持者」がどのよう人かに注目した。「ラストベルト(rust belt)のように耳慣れない言葉が飛び交い、それは「不満を持つ白人」としてレッドネック(redneck)のような表現とともに耳にはするものの、その実情はどのようなものなのか?
報道は多かったものの、その心理のインサイトや背景に迫ったものはなく、いかに表層的だったのか。つまり、彼らの心情については実は何一つ理解していなかったのではないか?
この本を読んで、改めてそう思った。著者はカリフォルニア大学の教授だが、表層的なジャーナリズムと、本物のアカデミズムの差を実感する。
ただし、この本はとても読みやすい。しかし、深い。著者の視点はニュートラルで、本当に米国の未来を深く考えていることに感動する。
そして、ワーキングクラスをめぐる課題は、米国だけのことではないわけで、どの国においても「自分事」となるだろう。
「なぜ、ワーキング・クラスは専門職に反感を抱き、富裕層を高く評価するのか?」
このタイトルの章では、こう書かれる。 >> 「トランプ支持者」でわかった気になってはいけない。『アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々【書評】の続きを読む
選手としては超一流で監督としての実績もある。ただし、振る舞いや言動には癖もあるので嫌う人もいるようだ。ところが、彼の悪口を言うと、言っている方が「アタマの悪い人」に見えるように思う。
とにかく、彼は自分で考え抜く。「考える」のではなく、「考え抜く」のだ。その思考がよくわかるのが、この「落合博満アドバイスという一冊で、これは野球の本というよりも「思考法」を学ぶ一冊ともいえるんじゃないだろうか。
既に多くの著作があり世評も高いが、この本は社会人野球の指導者を念頭に置いている。そのため、人材育成という面から読むと「ああ、なるほど」と納得することがあるわけだ。
落合という人は、基本的には合理主義者だ。この本にもあるが、高校の野球部を7回退部したというくらい理不尽なタテ社会を嫌う。また、トレーニングにおいても意味のない根性論を否定する。
ノックにしても「左右に振り回す」のはただのしごきであり、まず正面で捕球させることで正しい守備を知ることにつながるという。
ただし、この本を読むと「気持ち」の部分の大切さも強調していて、「合理的精神論者」とでもいうようなイメージを受けた。で、こうした「合理的精神論」というのは、ビジネスの世界でも大切じゃないかと思ったりもする。 >> 「合理的精神論者」の面目躍如『落合博満アドバイス』【書評】の続きを読む
それは、早川書房が潤うのではないかという期待からだ。カズオ・イシグロが好きであるとかそういうわけではない。ミステリ好きとして、早川が潤うのはありがたいのだ。
既に相当の話題になった文学賞だが、ふと気がつくと翌朝には「日本生まれで3人目の受賞」という見出しのメディアもあった。なんだ、これは。琴奨菊が優勝した時もそんなことがあったと思うんだけど、よく覚えてない。
まあそれはともかく、カズオ・イシグロ氏の作品はことごとく早川だ。そりゃ売れるだろう。
で、そういえば最近、早川はビジネスでもいい本を出しているんだよな、という話をしていたら、ノーベル経済学賞はリチャード・セイラー氏に決まる。『行動経済学の逆襲』も早川だ。心理学者でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カールマンの『ファスト&スロー』はマーケティングを生業とする者にとっては必読書のようになっているけど、こちらおなじく早川書房で文庫になっている。
そして、僕は気づいてなかったのだけれど、『重力波は歌う』という本も物理学賞の受賞者に取材した本だという。
早川の主力は、翻訳物のミステリとSFだ。東京創元社と並んで、好きな人にとってはとてもありがたい出版社である。
しかし、小説を取り巻く状況は厳しい。人口構成を見ても、もはや「日本語市場」が成立するか?というとこれはどんどん難しくなるだろう。日本人が日本語の訳で、世界中の本をそれなりに読めていたのは「人口ボーナス」があったからだ。
日本語は日本人以外は殆ど使わないので、どう考えても今後は大変だ。というか、既に海外で話題になった本の訳が、結構遅くなるケースが出ている。これは、文学でもビジネスでも学術でも、ジワジワと来ているのだ。 >> やっぱり『謎解き』とくれば早川書房なのだ。の続きを読む
 【読んだ本】ジョシュア・ハマー著/梶山あゆみ(訳)『アルカイダから古文書を守った図書館員』紀伊国屋書店
【読んだ本】ジョシュア・ハマー著/梶山あゆみ(訳)『アルカイダから古文書を守った図書館員』紀伊国屋書店
私たちは、本当にイスラム文化のことを知らない。いや、そうやって勝手に「私たち」としてしまうのは、ちょっと強引かもしれない。でも、少なくても僕の知識なんかは相当適当だ。
そして、アフリカを舞台としたイスラム文化史のこととなると、過去はもちろん「いま何が起きているのか」もあまりに無知であることを痛感した。
ヨーロッパで印刷革命が起きた16世紀には、アフリカでは多くの書物が存在していた。それは、おもに個人の手で保管されてきたが、1980年代以降に徐々に収集されて、やがて図書館が建設される。
このノンフィクションの舞台は、西アフリカのマリ共和国のトンブクトゥという都市で、主人公はアブデル・ハデル・カイダラ。彼は研究者だった父の仕事を受け継ぎ、若い頃から国中を行脚して古文書を集めていく。まず、その苦労話から物語は始まる。
やがて収集が進み、米国の財団からの援助もあり図書館をつくる。文芸書から法学、あるいは天文学や医学にいたるまで実に幅広いカテゴリーの書物がアフリカにはあった。
それは長いこと埋もれ「ないもの」とされていたのである。
本書ではあるイギリスの歴史家が1963年にBBCのインタビューで語ったことが引かれている。
「あるのはアフリカにおけるヨーロッパ人の歴史のみ。それ以外は、闇が広がるばかりだ」
そんな“常識”を覆して、新たな文化の歴史を文字通り「発掘」していくのだが、やがてアルカイダの勢力がこの国にも広がっていく。 >> 寛容なイスラムを知るためにも『アルカイダから古文書を守った図書館員』【書評】の続きを読む
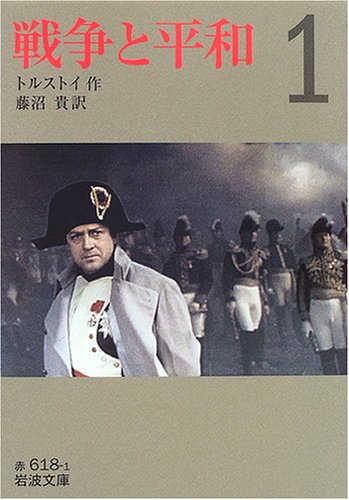 ふと思い立って春の連休に『戦争と平和』を読もうと思い立った。なぜそう思ったのかわからないのだが、読み始めたのは結局5月4日だった。
ふと思い立って春の連休に『戦争と平和』を読もうと思い立った。なぜそう思ったのかわからないのだが、読み始めたのは結局5月4日だった。
若い頃に躓いているのだが、どこで躓いたいのかもわからない。ほとんど、初読のようなものだ。
当然「連休に読む」などということ自体が無理な話で、読み終わったのは7月15日だった。
kindleで読んだのだが、文庫だと一巻あたり500ページ以上あって、全部で3000ページくらいなんじゃないか。『戦争と平和』以外にも30 冊ほど読んでいたので、2ヵ月ちょっとで読めたのは上出来な方かもしれない。
読み終わってみると、思ったよりも面白かった。子どものような感想だが、まずはそう感じる。そして、子どものような感想の続きを少々。
まず、タイトルをわかりやすく書き換えると『戦争と宴会』かもしれない。この小説は、ナポレオン戦争時のロシア社会を描いているが、出てくる人のほとんどは貴族だ。
そして、戦争シーン以外は貴族の日常であり、そのほとんどは宴会のような感じだ。あとは狩猟とかオペラとか。まあ、宴会というほどじゃなくても、家の中でメシを食いながらああでもないこうでもないと話してる。
ワインを飲むシーンもよくあるが「ドライマディラ」や「ラインワイン」に「ハンガリアン」とかも出てくる。さすがに、ナパバレーとかは出てこないけれど、よく飲んでいる。 >> 『戦争と平和』を読んで~ちょっと子どものような感想だけど。の続きを読む










