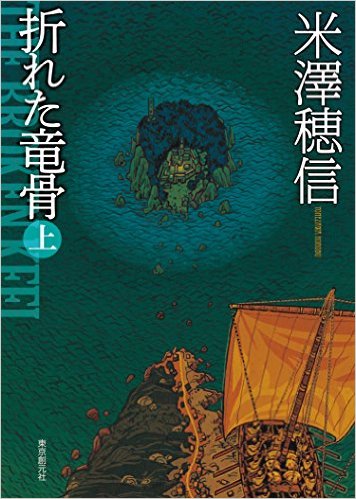マックス・ウェーバー 著 中山元(訳) 『職業としての政治』 日経BP社
マックス・ウェーバー 著 中山元(訳) 『職業としての政治』 日経BP社
===========================================
100年前の分析や批評が、いまでも通用する分野ってどのくらいあるのだろうか。
スポーツはまず無理だろうし、経済学も困難だろう。自然科学に至っては、話の前提が全く違っている。相対性理論は発表されていたが、重力波はもちろん、DNAも知られてない時代である。
ところが、政治をめぐる議論というのはちょっと趣が異なる。以前書いたマキャベリの『君主論』はいま読んでも頷くところが多いし、孔子や老子、あるいは古代ギリシャの議論も未だに通用する。
権力のあり方を巡るテーマの本質には普遍性が色濃い。恋愛を巡る心情もそうだが、両者ともある意味科学では説明しきれない側面がある。まあ、結局人がもっとも学べていない分野なのだろう。
この本は、1919年におこなわれた講演、つまり第一次大戦後の時代のものだ。政治家のあり方をめぐる課題は、現代においても十分に通用する。
日本はもちろん、混迷する欧州や大統領選で揺れる米国を重ねあわせて読むことができるし、ウェーバーが本質を見抜いていたことに驚く。
昨夏に、『プロテスタンティズムと資本主義の精神』について書いた時、想像以上の反響があったのだが、それだけ読みごたえがありつつ、洞察力に満ちた思想家であることを再認識した。
政治家に必要な資質を、「情熱・責任感・判断力」とキレよく述べつつ、その情熱は「不毛な興奮」ではないと釘を刺す。
一方で二種類の大罪があり、それは「仕事に献身しない姿勢」と「無責任さ」であり、虚栄への欲望のためにこの罪を犯す誘惑に駆られると述べる。
いわば、「100年コピペ」とでもいうべき、政治家のあるべき姿への洞察が語られているのだ。 >> 【GW本祭り】100年経っても色褪せないのは、いいことなのか、それとも…『職業としての政治』の続きを読む
================================
米澤穂信氏の作品が、ミステリー小説の人気ランキングの上位常連、というか言わば“V2”を達成するなど人気になってる。週刊文春や「このミス」などの年末恒例の投票で、一昨年は『満願』、そして昨年は『王とサーカス』が1位になった。
『満願』は短編集で、舞台は日本の日常的なシーンである。そこに隠された人間模様が伏線になり、事件が起きて謎が明かされる。どこか連城三紀彦を連想させるが、同じような感想を持った人は多かったようだ。
『王とサーカス』は、カトマンズを舞台にした作品で、21世紀初頭に起きたネパール王室殺人事件を題材にしている。主人公は元新聞記者のライターで、騒動のさなかに別の事件に出くわすことになる。
個人的な感想を言うと「悪くはない」という感じだろうか。一年間にあれだけの作品が発刊される中でのトップなのかと思うと、少々複雑だ。
まあ、横山秀夫の『64』も、冗長さだけが鼻について全く良いと思わなかった。なんか評判の料理屋に連れて行ってもらって、適当に相槌打ちながら食べているような感じだ。本でも料理でも、世間の好みとずれていることは多々あって、それで何の不自由もないから別にいいんだけど。 >> 【GW本祭り】『王とサーカス』に?な人には、『折れた竜骨』をぜひ。の続きを読む
昨日のつづき。
「CMを科学する」で紹介されている最新のテクノロジーを組み合わせることは、マーケティングや広告の世界に大きな影響を及ぼしていくと思う。その流れについて簡単にまとめておこう。
まず広告主企業だが、宣伝担当はもちろん経営レベルでも再度CMのあり方を見直す機会になるかもしれない。広告費は企業の利益水準によって上下する。近年だとリーマンショックの後の減少は相当厳しかったが、それ以降は東日本大震災と除くと、それほど強い逆風もなかった。
しかし、景気には波があり、次の下り坂において「単純な出稿減」にするのか、「戦略的プランニングへの転換」にするのかで、その企業の明暗が分かれると思う。
あらゆる経費が費用対効果を問われる中で、「専門家」に任されていたのがこの分野だ。ただし、その専門家が最新のノウハウを駆使できないとなれば、どうなるだろうか。
効果のないマーケティングコストをかけているとすれば、それは経営の責任だし、株主から見ても問題だろう。そういう意味で、宣伝担当にはとどまらない話だと思う。 >> 広告ビジネスの「器量」が問われる。『CMを科学する』の続きを読む
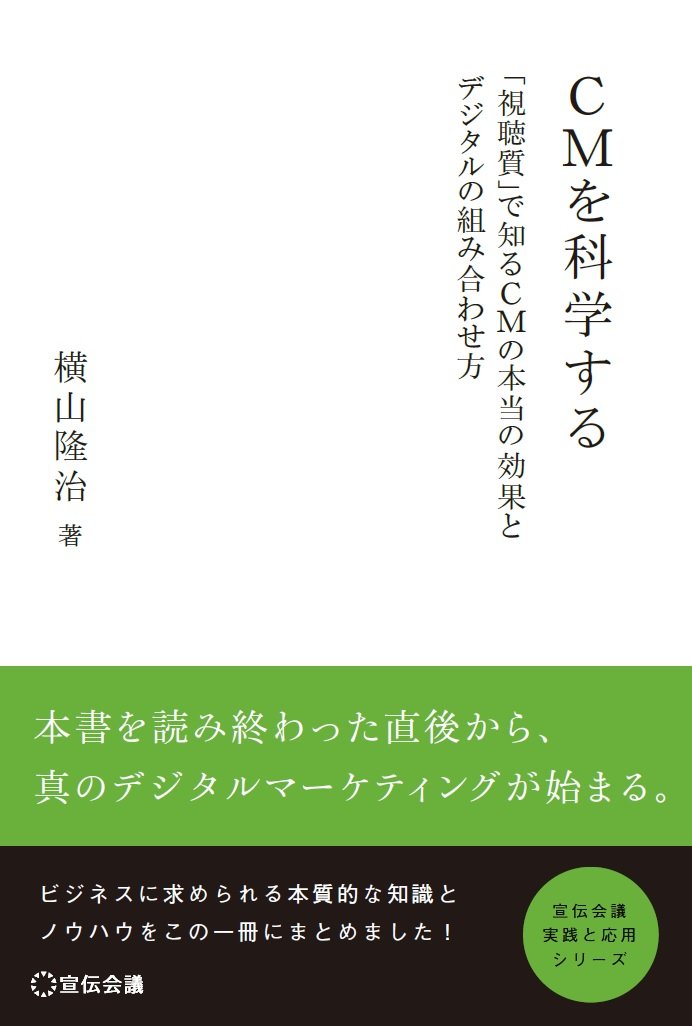 「科学する」というのは、結構昔からある言い回しだが、いったいどんな本が他にあるのかと思ってamazonで検索してみた。一番最初に出てくるのは本書だが、次にあったのが『科学する麻雀』だった。
「科学する」というのは、結構昔からある言い回しだが、いったいどんな本が他にあるのかと思ってamazonで検索してみた。一番最初に出てくるのは本書だが、次にあったのが『科学する麻雀』だった。
他にも、いろいろ出ているが共通点がある。それは「勘や経験あるいは言い伝え」に頼っている分野ということだ。
CMについては、科学的分析もおこなわれている。ただし、いま敢えてこのようなタイトルの本が出ることには大切な意味がある。なぜならCMを取り巻く科学は相当に進歩している一方で、多くの人はその最先端を知らないままにビジネスが進んでいるからだ。
この本に書かれている科学の対象は大きく2つある。
1つは「どのような人に到達しているか」という、メディアプランニングに結びつけるための数量的分析だ。
そして、もう1つは「どのように心を動かしたか」という、クリエイティブの課題、つまりメッセージ開発につなげるための合理的アプローチとなる。
メディアとメッセージ。広告の効果は、その相乗効果にある。多量に出稿しても、クリエイティブによって「残り方」が異なることは以前からわかっている。
一方で、どんな印象的なクリエイティブでも出稿量が少なければ、効果は限定的だ。
メディアとメッセージ。これは広告の両輪であり、広告代理店がビジネスとして成立する理由は、この2つの分野の専門的スキルを持つ人材を擁して、かつ組織としてデータを保有分析してきたことにある。 >> 『CMを科学する』テレビCMの新約聖書は想像以上のインパクト。の続きを読む
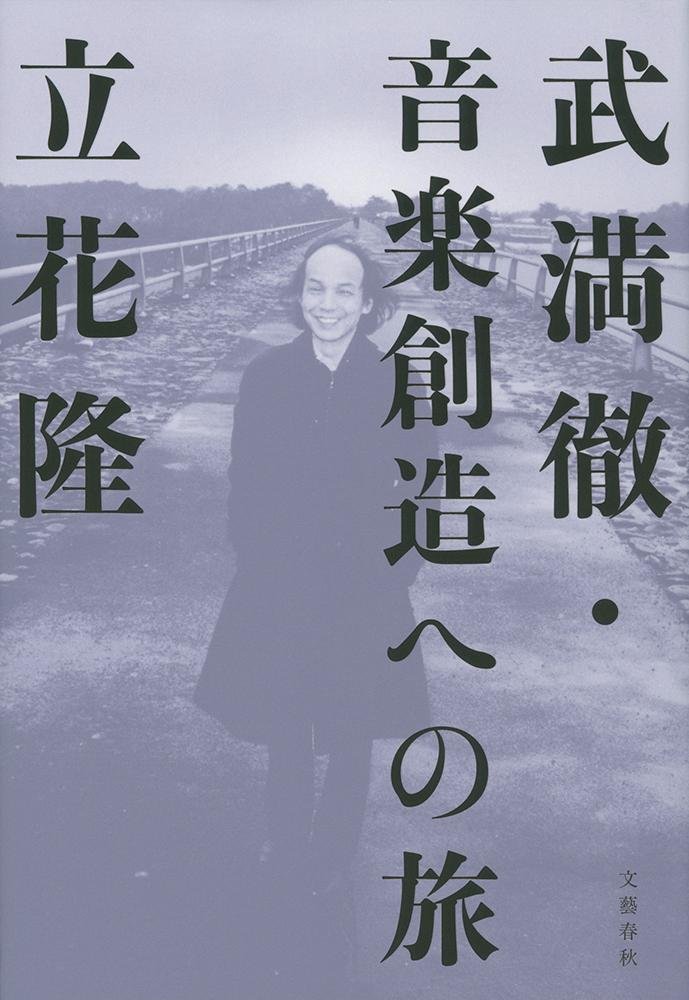 【読んだ本】立花隆 『武満徹・音楽創造への旅』 (文藝春秋)
【読んだ本】立花隆 『武満徹・音楽創造への旅』 (文藝春秋)
武満徹が亡くなって20年になる。
仮に生きていれば、いま85歳ということだが、同年代の黛敏郎、5歳ほど上の芥川也寸志、團伊玖磨ら「三人の会」のメンバーも鬼籍に入った。團を除くと、60代半ばで逝っている。盟友の小澤征爾が80歳で闘病を経てタクトを握っているが、「戦後楽壇」のうねりは大きな潮目を迎えている。
「武満徹・音楽創造の旅」は、立花隆が武満に対しておこなった長時間のインタビューをもとに、その創造の歴史を追っていくドキュメンタリーだ。核になるのはインタビューだが、もちろんそれだけではない。関連する文書を探り、関係者の証言などを交えて再構成される。
それは、武満徹の創造性を訪ねるだけではなく、日本の戦後文化をもう一度再確認する旅でもある。だから武満という人物の評伝であるとともに、「文化史」の文献としてもとても貴重なものだ。
ただし、この本はまた異様な存在感を放つ一冊でもある。800頁に近い大作であるというだけでなく、武満と立花の思い入れのようなものが凝縮されている。そして、暗い伏流が、影のように通底しているように感じる。
それは、この本が成り立った過程にあるのかもしれない。 >> 渾身の日本戦後文化史『武満徹・音楽創造への旅』の続きを読む