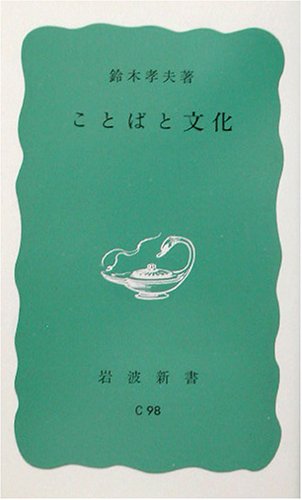子供が親を「呼び捨て」「ちゃん付け」 そんな親子は「気持ち悪い」か
5月23日のフジテレビ系「バイキング」で「子どもが親を名前やちゃん付け」で呼ぶことを許せるかどうか?というテーマだったそうな。
番組の視聴者アンケートでは3割ほどが「許せる」ということだが、教育評論家などは「好ましくない」という話だ。まあ、「どんどんやれ」というコメントにはならないだろう。
ただ、十代の若者が家族に対していだく感覚は結構前から変化している。「おばあちゃん、かわいい」みたいな言い方に戸惑ったという話も、15年以上前だったと思う。いま調べたら「かわいいおばあちゃんになりたい」みたいな記事が出てきた。
で、「家族をお互いにどう呼ぶか」というのは、言語学や日本語論の分野でも結構面白い。この議論を提示したのは、慶応義塾大学の言語学者の鈴木孝夫氏だが、「ことばと文化」はいま読んでも本当に奥が深い。
言語学の概略から文化論まで、まさに縦横無尽に語ってくれる。
1973年の出版で、海外事情の紹介などは、いま読むとやや時代を感じるが、論旨の骨格は太い。amazonの言語学カテゴリーでは1位である。 >> 「家族をどう呼ぶか」は日本語ならではの問題だった。の続きを読む
 深緑野分 『戦場のコックたち』 早川書房
深緑野分 『戦場のコックたち』 早川書房
最近、日本のミステリーの新作を読むと、なんかスッキリしないことが多かった。
先日書いた「王とサーカス」とか「64」とか、まあ世間の評判と自分の好みがズレているんだろうけど、この「戦場のコックたち」には結構引き込まれた。
ミステリーとしていろいろ突っ込むとキリがないかもしれないが、「次作も読んでみたい」と感じがする。デビューの短篇集に続いて、これは初の長篇となる。
ただし、いわゆる「連作」というスタイルだ。プロローグとエピローグを挟んで5つのエピソードが語られる。ただ、登場人物は同一という体裁だ。
というように書くと、北山薫のシリーズを思い起こすかもしれないが、タイトルとおり舞台は戦場だ。人は次々と天に召される。
この小説が意欲的だな、と思うのは、まず舞台の設定だ。第二次世界大戦の末期、あのノルマンディー上陸作戦に参加した米軍の群像を描いている。主人公はいわゆる「特技兵」で、タイトルの通りコックだ。 >> ジンワリ響く群像劇のミステリー『戦場のコックたち』の続きを読む
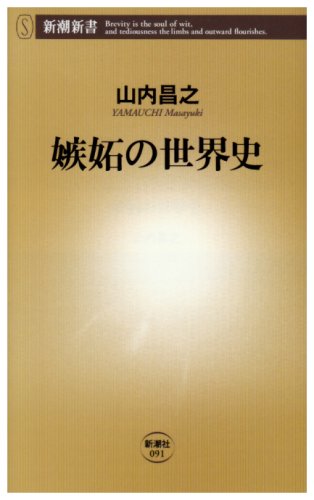 最近はいろんな会社で、経営者をめぐる騒動が目立つ。昨日はベネッセのニュースが目立ったけれども、セコムの会長社長解任というのも驚いた。もっとも驚いたのはセブン&アイを巡る一件だったけれど、経営者を決定するシステムが変化していく過渡期にある中で、今後もこうしたことは起きていくのだろう。
最近はいろんな会社で、経営者をめぐる騒動が目立つ。昨日はベネッセのニュースが目立ったけれども、セコムの会長社長解任というのも驚いた。もっとも驚いたのはセブン&アイを巡る一件だったけれど、経営者を決定するシステムが変化していく過渡期にある中で、今後もこうしたことは起きていくのだろう。
『社長解任 権力抗争の内幕』という本が出ていて、これはさまざまな会社の経営実権をめぐるドキュメントだ。2月の出版で、東芝の騒動が最後に描かれるが、多くは昭和のケースである。住友銀行、関電、新日鐵あるいはフジサンケイグループなども取り上げられる。さまざまなトラブルのあとで、立ち直った企業もあれば、どこか引きずっている企業もあるのだろう。
それにしても「今とは時代が違うよな」と感じる点もあった。
1つは労働組合の存在感だ。いまとは比較にならないほどに大きい。ここまで経営に介入していたのかと改めて思う。
もう1つは、いわゆる「裏社会」とのかかわりだ。現在においてどうなっているかは何とも言えないが、想像以上に露骨な時代もあったのだと感じる。 >> 男の嫉妬が会社を揺らす。『嫉妬の世界史』の続きを読む
以前勤めていた会社の後輩にあたる、斎藤迅さんから「一瞬でやる気を引き出す38のスイッチソング」 を恵送頂いた。
カテゴリーを超えて様々な曲がリストにあって、それは音楽が人々を励ましてきた歴史の縮図のようだ。
その中で「ふるさと」についても書かれていた。本書には数少ない日本の曲だが、この詩にはちょっとした仕掛けがあり、そのことを僕は高校の先輩から聞いた。高野辰之 による有名な歌詞は次の通りだ。
兎追いし かの山
小鮒釣りし かの川
夢は今も めぐりて、
忘れがたき 故郷
如何に在ます 父母
恙なしや 友がき
雨に風に つけても
思い出ずる 故郷
志を はたして
いつの日にか 帰らん
山は青き 故郷
水は清き 故郷
よくある話だとは思うが、子供の頃は「うさぎ美味しい」だと思ってた。昔の田舎ならそんなものだろう、と思ってたのだ。もちろん「ジビエ」など知るわけもない。 >> 「ふるさと」が誰にとっても名曲である理由。の続きを読む
妻が恩田陸の小説を読んでいたのだが、惹句を読むと「超巨大台風のため封鎖された空港。別室に集められた11人の中に、テロ首謀者がいるというらしい」あ、これはどこか既視感があって、まさに「11人いる!」ではないか。
恩田陸は、萩尾望都からの影響を受けていると言っているが、萩尾望都の作品が他の作家に与えた影響は相当広範にわたっていると思う。
文庫版『ポーの一族』には、宝塚歌劇の小池修一郎や作家の宮部みゆきがエッセイを寄せているが、宮部は萩尾を「多くの後続の作家のエネルギー源」と書いている。コミックはもちろん、小説や映画や舞台、あるいはゲームまでその影響は広い。直接彼女の作品を知らなくても、さまざまなクリエイターを通して知らぬ間にその世界を感じていることも多いだろう。そういえば「11人いる!」というドラマもあった。宮藤官九郎の作品である。
というわけで休み中に『11人いる!』を読み、と初期の傑作群を読み返して、やはり嘆息してしまう。『ポーの一族』を連載している間に、『11人いる!』『トーマの心臓』と送り出すわけで、「才能が迸る」とはまさにこういうことだったのか。どれも20代の仕事だ。 >> 【GW本祭り】晴れた初夏の午後に、『ポーの一族』。の続きを読む