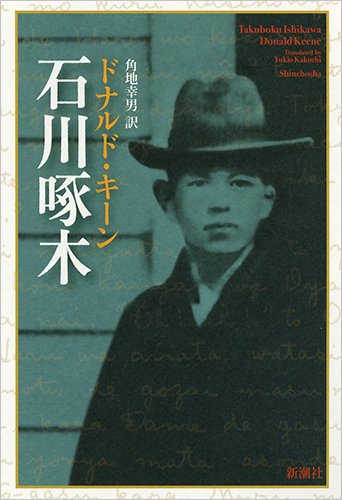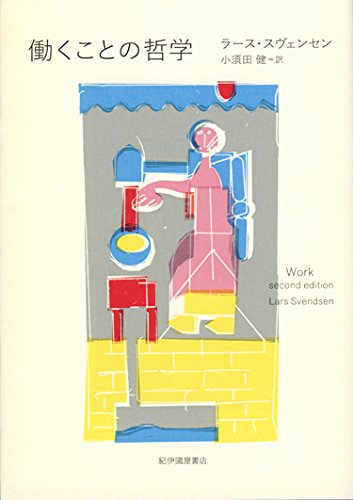 なんども書いてしまうのだけれど、今年を振り返る時に「働きかた」についての話は、とても気になる。ただ「働きかたについての“議論”」というところまで、行っているように思えない。
なんども書いてしまうのだけれど、今年を振り返る時に「働きかた」についての話は、とても気になる。ただ「働きかたについての“議論”」というところまで、行っているように思えない。
時間管理や、副業あるいは在宅勤務などの手法的な問題も大切だろうけど「なぜ、何のために働くのか?」という問いがどこかに行っている。
どれだけ働く環境を整えても、意志と目的を失えば人はいつかは病むかもしれない。それは、すべての働く人にとっての課題だろう。金銭的対価を受け取らないいわゆる「専業主婦」だって同じだと思う。
そして、働き方をめぐる議論は妙な拡散を見せている。
今年は始まって早々に「囲碁とAI」のニュースが大きく報じられた。いままで関心のなかった人の興味を引いたのはいいけれど、案の定「人の仕事がなくなるのか?」という話になだれ込んでいった。
おもしろいことに、そういったことを心配する人ほど、目の前の仕事をきちんとやっていないが、メディアが不安を煽るのには格好の客だったのだろう。
その一方で、「適正な働き方」が問われた。こちらは、十年一日のごとく日本人の長時間労働がテーマである。今日は、電通幹部が書類送検されたようだ。
そういう中で、「働く意味」を正面からとらえた一冊が『働くことの哲学』(ラース・スヴェンソン/紀伊国屋書店)だ。筆者はノルウェーの哲学者だが、書いてある内容はいい意味で「普通の発想」だ。 >> 【2016読んだ本から】②働くことの哲学の続きを読む
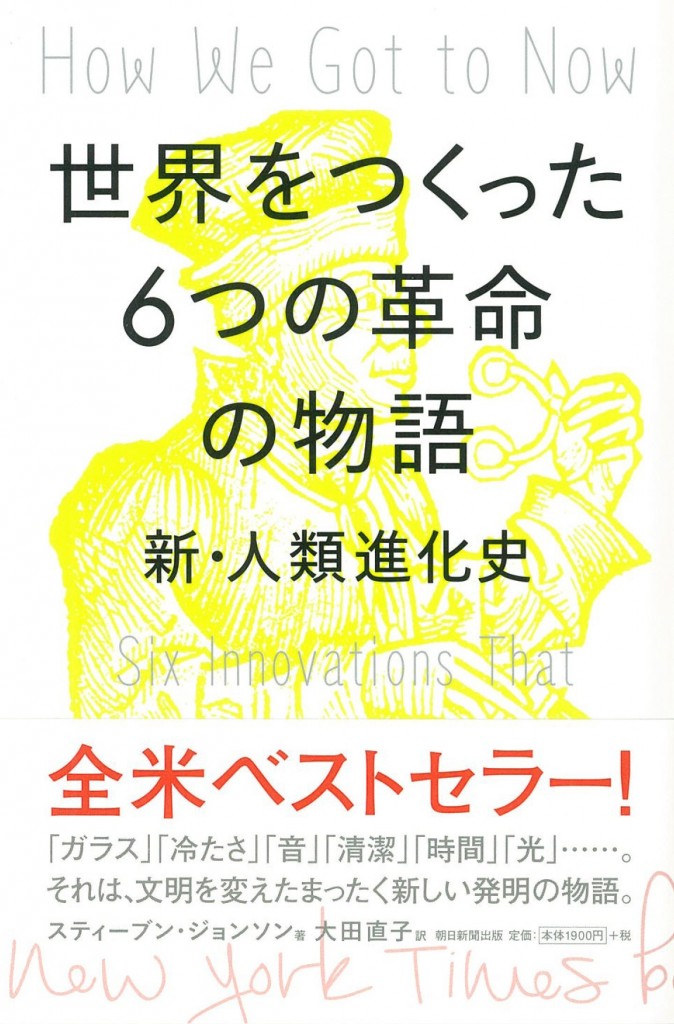 もう今年もわずかになったので、何か回顧系の話にしようかと思い、読んだ本を振り返ってみようかと思う。感想を書いた本も含めて、ザックリと見ていこう。まずは、歴史関連から。
もう今年もわずかになったので、何か回顧系の話にしようかと思い、読んだ本を振り返ってみようかと思う。感想を書いた本も含めて、ザックリと見ていこう。まずは、歴史関連から。
ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』以来、世界史をザックリと振り返る本がいろいろと出ている。僕も今年の3月にそうしたジャンルばかりを3回にわたって取り上げた。リンク先は①/②/③.
この流れにつらなるのが「サピエンス全史」(ユヴァル・ノア・ハラリ/河出書房新社)だろうか。帯に、ダイヤモンドの推薦コメントがある辺りが、「ああ、この流れだな」と感じさせてくれる。
人類学的な視点で「認知革命」「農業革命」を経て「科学革命」へという道のりを振り返りつつ、貨幣という“究極の虚構”に焦点を当てていく。
著者はイスラエルの研究者だが、欧米の歴史研究は「なぜ歴史は動いたのか」という根本に迫っている、この辺り日本とは、もう研究の土台からして別物なんだろう。
ただし、さすがに既視感もあるし、少なくてもダイヤモンドなどの先行研究を読んでおいた方がいいだろう。 >> 【2016読んだ本から】①なんとなく歴史系の続きを読む
伝記は難しい。事実を並べるだけなら年譜で十分だし、それなら各地にある「記念館」に行けばいいだろう。
しかし、伝記にも作者がいて、そうである限りは切り取り方が問われる。その記述が、伝記対象者の作品解釈にまで影響を与えることもあって、それが難しさの根っこにあると思う。
日本におけるベートーヴェンの「楽聖」イメージは、ロマン・ロランの伝記による影響が大きいが、それによって音楽そのものへの感じ方が偏向したとも言われる。
逆に「アマデウス」のように、一本の映画によってモーツアルトのイメージは大きく変わった。
伝記作者としての1つの方法は、事実をできるだけ多く集めて多面的に記述することだろう。その1つが今年刊行された立花隆の『武満徹・音楽創造への旅』だろう。
もう1つは作者の視点で情報を削ぎ落して構築する方法だろうが、この『石川啄木』はそちらの方に近い。
僕にとって石川啄木は、もっとも好きな歌人だ。とはいえ、学生時代から関心があったわけではない。30歳を過ぎた頃に歌集を読んで、改めて驚いた。 >> 日本人への贈り物。ドナルド・キーンの『石川啄木』の続きを読む
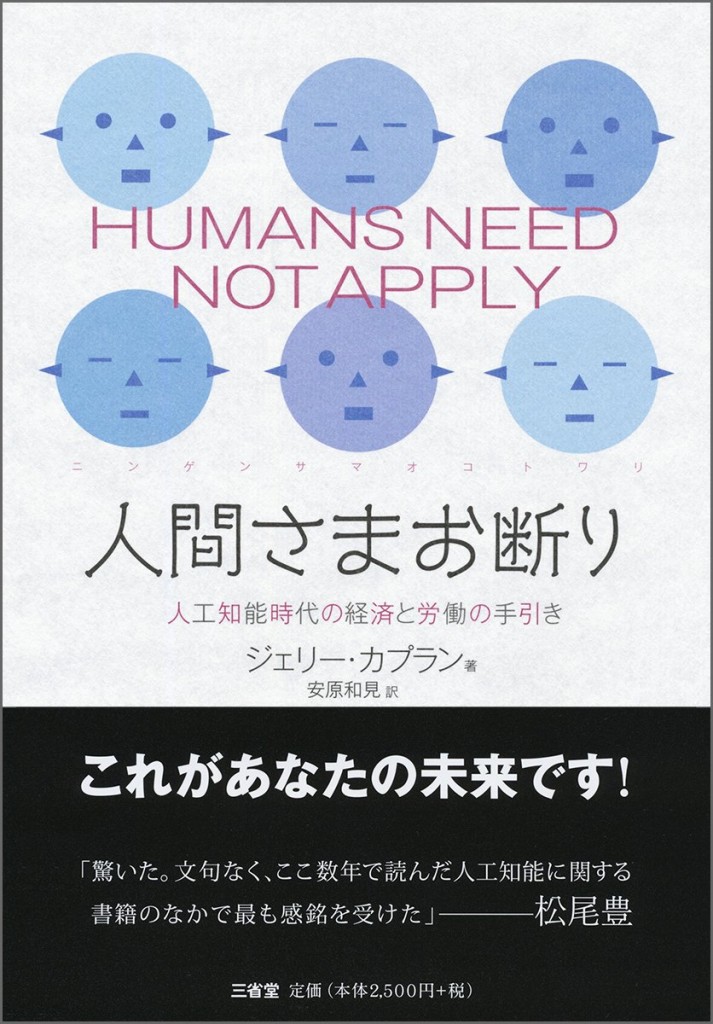 経済産業省が、実証実験として国会答弁をAIに下書きさせるというニュースがあった。SNSに記事をシェアしたら「虚構新聞か」という声があったが、妻は「星新一にありそうだ」と言っていた。
経済産業省が、実証実験として国会答弁をAIに下書きさせるというニュースがあった。SNSに記事をシェアしたら「虚構新聞か」という声があったが、妻は「星新一にありそうだ」と言っていた。
僕が気になるのはとても単純なことで、あんな答弁のような文章を学ばせたら、AIがダメになっていくんじゃないか。そのことに尽きる。
新年早々に、囲碁の勝利に始まりAIというのは実質上の「流行語大賞」なのではないかと思うが、「答弁AI」で何となく年末のオチという感じになってしまった。
とはいえ、AIを巡る本なども多く、その殆どは「未来」を論じるものだ。しかし、哲学的な深い考察がなされているものは、早々多くはない。
僕が読んだ中でお薦めしたいのは、この「人間さまお断り」だ。著者のジェリー・カプランはスタンフォード大学の先生であり、多くの企業にも関わった人である。
AIの入門書としては松尾豊氏の「人工知能は人間を超えるか」がお薦めだが、その松尾氏が帯にメッセージを寄せている。
「驚いた。文句なく、ここ数年で読んだ人工知能に関する書籍の中で最も感銘を受けた」ということだけど、この本は単なる予測や煽りではなく、AIの本質を突いていると思った。
たとえばロボットが「犯罪」を犯した場合はどうなるんだろうか?というお話。 >> トランプの「ロボット制限令」という妄想。~『人間さまお断り』はAI本の白眉の続きを読む
 タイトルには「皇室外交」と言う言葉が入っているけれど、そもそもこの言葉自体が宮内庁的には「非公認」らしい。皇室は、海外に訪問したり賓客を迎えたりするが、これはいわゆる「外交」とは異なるということなのだろう。
タイトルには「皇室外交」と言う言葉が入っているけれど、そもそもこの言葉自体が宮内庁的には「非公認」らしい。皇室は、海外に訪問したり賓客を迎えたりするが、これはいわゆる「外交」とは異なるということなのだろう。
しかし、実質的に皇室が海外諸国との関係に及ぼしている役割は相当にあるはずで、本書ではその辺りの事情をていねいに書かれている。
著者の西川恵は新聞記者の外信部で長年勤められていた方だが、「エリゼ宮の食卓」という名著がある。これは、フランスがエリゼ宮で晩餐会をおこなう時のメニューを分析することで、時の外交姿勢を解き明かそうとしたユニークな本だった。
本書でも、その辺りの話から始まる。皇室主催の晩餐会がフランス料理で、ワインもフランスの最高級のものを供する理由などから始まるので、とっつきやすい。
そして、日本の皇室だけではなく、海外の首脳や王室のエピソードも豊富だ。
たとえば、ホワイトハウスの晩餐も以前はフランス料理だったが、現在は米国の郷土料理などを意識したメニューに変わったという。
それはクリントン政権の時のことだが、先導したのはヒラリー夫人だったようだ。この辺りにも、いろいろな意味で政治家らしさを感じる。
あるいは、フランスのオランド大統領の「パートナー」として来日した女性にたいする皇后の気遣いなども印象的だ。
また、若い時に昭和天皇や今上天皇が欧州で見聞を広めたことが、後に及ぼした影響も興味深い。一方でオランダや英国が、第二次世界大戦で日本の交戦国であり、その爪痕が近年まで残っていた中で皇室の果たした役割は、やはり「外交」なんだと思う。 >> 外交を知ると日本が見える。「知られざる皇室外交」の続きを読む