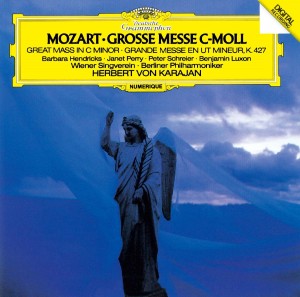 声楽というか広くヴォーカルというのは、苦手とまでは言わないけれど、「敢えて聞かない」音楽の方だった。だから、「好きな歌手」というのはカテゴリーを超えて特にいない。理由はよくわからないが、それだけ楽器による演奏が好きってことだろう。
声楽というか広くヴォーカルというのは、苦手とまでは言わないけれど、「敢えて聞かない」音楽の方だった。だから、「好きな歌手」というのはカテゴリーを超えて特にいない。理由はよくわからないが、それだけ楽器による演奏が好きってことだろう。
まあ、何の説明にもなってないし、どうでもいいような話に聞こえてしまうだろうが。
ところが、ある時に楽器の音をまったく聞く気がしなくなった。というよりも、音楽を聞く気分になれない。
それが、5年前の震災からしばらくの間に起ったことだった。
オーケストラは何を聞いても耳障りに感じられて、かといってピアノや室内楽だと「国営放送がとりえあず無難な音楽を流してます」のようで、それもまたしっくり来ない。
そのうち、声楽の曲なら聞いてもいいような気分になって、手元のディスクを聴いてみると、スッと気持ちが柔らかくなったように感じられた。いきなり「レクイエム」などを聞く気にもならず、とはいえオペラもお門違いのような気がしたので、モーツアルトのミサ曲ハ短調を聞いてみた。カラヤンとベルリンフィルのディスクだ。
それからは、そうした声楽曲ばかり聞いていた。そのうち、いろいろな音楽を聞くように戻っていったが、声楽曲を聞く機会は増えた。
「人間の声は究極の楽器」という表現を聞くことがあるが、それは発想が捩れているような気もする。むしろ、すべての楽器は声のように歌えることを目指しているようにも感じる。
なぜ、あの頃に声の音楽だけを受け入れられたのかはわからない。そうした話を聞いたことはないので、もっぱら個人的な感覚だったのだろう。
今日の東京は朝から冷えているが、東北では雪になるところもあるようだ。5年が経ち、さまざまな人が、それぞれの時間を過ごしているのだろう。僕は、その頃の音楽を聞きながら、ひとりで仕事をしている。
どうやら、小雨が降ってきたようだ。
 国内の美術館の多くは都市部にあるが、郊外や山麓などにもユニークなものが結構多い。
国内の美術館の多くは都市部にあるが、郊外や山麓などにもユニークなものが結構多い。
関東圏だと箱根や信州などの観光地に有名なものがあるが、その他にも千葉県の川村記念美術館や群馬の大川美術館など、「そのために」行くような立地の施設もある。
今回行ったのは信楽のMIHO MUSEUM(ミホミュージアム)だ。「信楽」というのも関東在住の者にはなかなかピンと来ない。狸で有名な信楽焼の町らしいとわかるが、アクセスを調べると石山駅から送迎バスで50分というが、石山駅というのもよくわからない。
結局、京都からレンタカーを借りて向かうことにした。1時間くらいで行けそうなのだ。そうなったら京都へも行こうかということで金曜の朝に出立して、その日はミホミュージアムへ行き、京都に戻って日曜夕まで滞在しようという計画にした。
ミホミュージアムは前々から関心があった。コレクションに定評があるし、建造物としてもユニークだという。今回は伊藤若冲の「樹花鳥獣図」が静岡県立美術館よりやって来て、プライスコレクションの「鳥獣花木図」と一緒に展示される。
後者の方は、2006年の東京や2013年の福島でも見たが、前者の方は静岡へ行こうかと思いつつタイミングを逸していた。 >> 向かい合う若冲~春のミホミュージアムの続きを読む
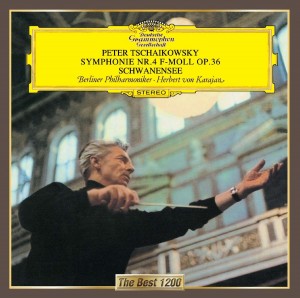 チャイコフスキーの交響曲は、初めの3曲と、後の3曲でガラリと変わる。1番から完成度の高い、ブラームスやマーラーと異なり「化けた」感じがするが、3曲の個性は全く異なるのが面白い。
チャイコフスキーの交響曲は、初めの3曲と、後の3曲でガラリと変わる。1番から完成度の高い、ブラームスやマーラーと異なり「化けた」感じがするが、3曲の個性は全く異なるのが面白い。
ただ、僕がコンサートで聴きたいのは圧倒的に4番だ。
6番の「悲愴」は音楽史に残る名曲だと思うが、しんどい。海外のオケは結構演奏することが多いのだが、躊躇してしまう。一方で、日本のオケだと「名曲コンサート」のようなプログラムに収まることが多く、これはこれでどうも食指が動かない。
5番は、学生のオケとの相性は最高だと思う。フィナーレのコーダに入る辺りは、それまでの想いが迸るようでようで、独特の盛り上がりをみせる演奏を聴くことも多い。ただ、プロが演奏すると意外にスルスルと終わってしまう。海外のオケなどフィナーレの金管も軽々と吹くが、アマオケだとそこが懸命になるので妙な高揚感が出るのだろう。
というわけで、4番だが、これはこれで曲者だ。1楽章はトリッキーなリズムで随所に罠がある。プロでもガタガタになることがあって、大昔N響が破滅的な状態になったことがある。
その演奏はオンエアされたために、学生時代に半ば伝説のようになっていた。トランペット奏者がのちにインタビューで語っていたことがあるが、ティンパニーと目配せして「エイや!」でファンファーレを吹いてどうにか収めたそうだ。ああ、あの辺かと見当がつくかもしれない。
4番は1楽章が妙に長い。そのために、バランスが悪いという人もいるが、それはディスクの演奏時間を眺めた上での話だと思う。実際に生で聞いて楽章バランスなどは気にならない。「一楽章偏重」の悲愴やピアノ協奏曲も同じことだろう。
この交響曲の魅力は「絶妙に破綻」しているように聞こえるところだと思う。5番は形式的にはまとまり過ぎるくらいまとまっているし、6番は破綻それ自体を音楽にして恐ろしい完成度になっている。
それに比べると4番はきちんとしているようで、音楽がどこに流れているか分からず、崖沿いの道をハイスピードで走るようなスリルがある。そうやってワインディングを走ると、妙な亡霊がフワリと現れる。
フィナーレなど、盛り上がって終わるのだが、それほどの「勝利感」も漂わない。手紙には冒頭の動機を「運命」と書いているが、そういう表題的な解釈なしに音のうねりを楽しむ曲のようにも思う。
ディスクは、カラヤンとムラヴィンスキーが昔から双璧のように言われている。これは好みもあるので、星をつけるような野暮はしないけれど、僕はカラヤンの60年代の録音が一番好きだ。その後の録音も聞いて思ったのだが、4番の場合この録音がムダにパワフルで直線的なのだ。
オケも指揮者も「すいません、よく考えてませんでした」という感じで一気呵成にフィナーレまで進むのだが、それで交響曲が成立しているのもまた驚きなのである。
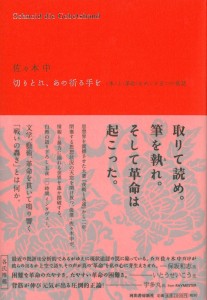 僕は本については、子どもの頃からいろいろ読んでたと思う。ただし、古典などにもいろいろ穴があるし、いわゆる乱読の方だろう。
僕は本については、子どもの頃からいろいろ読んでたと思う。ただし、古典などにもいろいろ穴があるし、いわゆる乱読の方だろう。
そして、ある頃まで多読がいいと思っていた。今でも自宅の仕事場にオーダーメイドの本棚がありつつ、トランクルームを借りている。ただし、ここ何年か考えが変わってきた。どうやら、本をたくさん読んだからといって、それ自体に本当に価値があるのだろうか。
きっかけは佐々木中の『切りとれ、あの祈る手を』という本を読んだことだった。2010年秋の本だが、修善寺へ旅しながら読んだ。
「本は少なく読め。多く読むものではない」これは、多くの文人が言ってきたという。ただし、それがスッとわかるにはタイミングがあるように思う。僕は「そうだよな」と思ったのは、ちょうど40代半ばで単なる多読への疑問があったのだろう。
まず「繰り返して読みたい本」ってそんなにはない。ところが、繰り返して読む本には、よむたびに発見がある。「一度だけ読む本」がどんどん家の中に増えて、そこからはみ出していく中で、果たして「蔵書」に何の意味があるのか。それって、背表紙をズラリと並べることへの満足だけなんじゃないか。
一方で、僕は「聖書」一冊も満足に読んでない。これから頑張れば読むことは可能かもしれないが、そもそも聖書は「一通り読む」ものではない。その言葉から、何を読み取り考えるべきか、ということは千年の単位で議論されてきた。そして、今でも聖書一冊に一生を費やす聖職者の方がいる。 >> 本をたくさん読むのはいいことなのか?の続きを読む
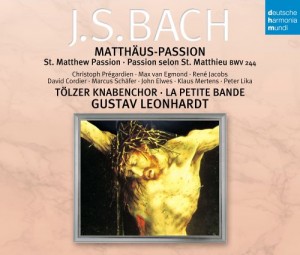 都市伝説の類で真偽を確かめたわけではないが、かつて英国小説の訳でこんな感じの一文があったという。
都市伝説の類で真偽を確かめたわけではないが、かつて英国小説の訳でこんな感じの一文があったという。
「彼はレコードに針をおろして、“ジョンの情熱”のメロディーに耳を傾けた」
さて、“ジョンの情熱”というポップスはあるかもしれないが、どうも怪しい。実はバッハの「ヨハネ受難曲」だったというのがオチなのだ。ヨハネ受難曲はJohn Passion、受難曲は英語でpassionとなる。そんなタイトルの映画もあったと思うが、まさにキリストの受難と磔刑を描いていたはずだ。
どうして、passionにそういう意味があるのか?というのを調べるといろいろ出てくるだが、結構複雑なのでここでは細かく触れない。
ちなみに、今は復活祭(イースター)に向けた四旬節の真っただ中だ。四旬は40日だが、日曜を除くので実際は46日間。復活祭は春分の日以降の、最初の満月の次の日曜日なので、今年は3月27日。
受難曲はこの季節に演奏会が開かれることが多い。そして、取り上げられるのは「マタイ受難曲」だ。ただし、ついつい聴く機会を逸する。年末の第九のように、あちらこちらでやってるわけではない。日本では年度末の時期にあたるし、気がつくと「ああ、終わってた」ということになる。今年は行く予定だが。
マタイ受難曲は、マタイによる福音書を題材している。ものすごく大雑把にいうと、聖書の言葉に曲をつけて、適宜加筆しながら全体を構成したものということになる。最後の晩餐、ユダの裏切り、ペテロの否認と有名なシーンが続く。
こう書くとわかりやすそうに見えるが、なんといっても題材が受難だ。聴く方にも、それなりのエネルギーがいることはたしかだ。
ただ、ふとしたきっかけでつき合い方が変わった。 >> 【音の話】復活祭までの四旬節に、マタイ受難曲。の続きを読む








