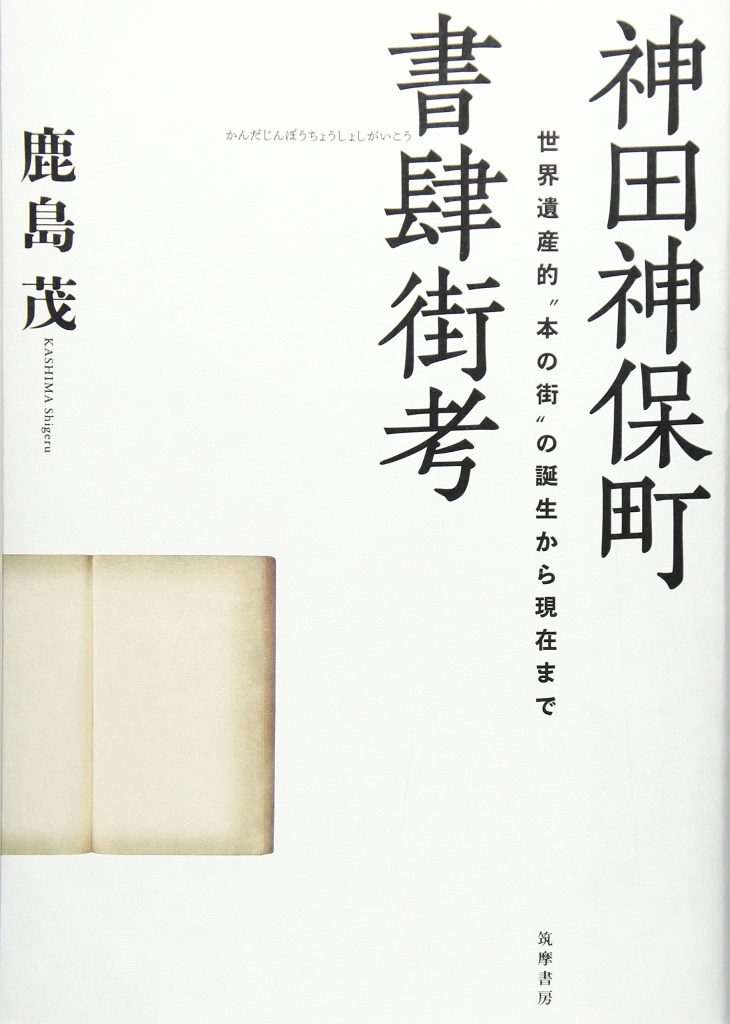大学を卒業して入った会社の本社は神保町にあった。住所表記は神田錦町だが、ざっくりと神保町エリアだ。1ヶ月半の研修の後に丸の内で働くことになり、その後はしばらく疎遠だったが30歳の頃に神保町のオフィスの部署に異動した。
それから3年近くは、神保町勤めだったが、最高の環境だった。仕事が研究開発だったので書店に行くのは「仕事」だ。毎日のようにウロウロして、喫茶店に行ってた。そのうち、さすがに忙しくなってきたが、それでも自分のペースで働いていた。
この本は明治以降の、神保町の「書肆街」ができていく過程を追っているのだが、街の成り立ちを通じて、日本の知的文化の形成を追っている本でもある。
だから書肆街の話にならず、わき道にそれるのだがそれがまた面白い。東京大学の前身、開成学校から、明治、法政、中央、専修などが創立される過程にある種の必然性があることがわかり、またそうした学校と古書店街との縁もよくわかる。
もちろん、出版社や書店の歴史については個別にも詳しいし、なぜ靖国通りの南側に古書店が密集しているのか?という理由も「ああ、なるほど」と納得できるだろう。
しかし、僕が関心を持ち、かつこの街の将来にやや不安を覚えるのは、書肆街が想定外の追い風、あるいは「神風」のようなものに支えられてきたという歴史だ。
1912年には神田の大火で、多くの古書店が消失する。この際に、和本は壊滅的になったが、洋装本(つまり今の本の形態≠洋書)の店は、巷に潜在的ストックが多く立ち直り、現在の姿の基礎を作った。
また大学が焼けたために、再出発の際に古書店に注文が殺到したという。
関東大震災の後も、灰燼に帰したものの、しばらくたつとやはり被災した多くの学校から注文が来て、「バブル」のような状態になった。
それは、太平洋戦争後でも同様だ。預金封鎖もプラスに働き、大学は再建のために古書を買い入れる。そして、神保町の古書店は殷賑をきわめた。
では、将来はどうなのか?と考えるとあまりいい予感はしない。なぜなら、「神風」のようなものに支えられた業界というのは、往々にして商いの知恵を絞ろうとしない。またいつか風が吹くだろう、という気分になってついつい時代の流れを読み損なうことがあるからだ。
最近で言えば、「地デジ景気」の後にガタガタになった日本の電機メーカーがいい例だろう。
著者の鹿島氏のように神保町を心底愛している人はたくさんいる。しかし、ちょっと距離を置いて見た時に、その街の価値はジワジワと落ちている。
馴染のある街だけに残念にも思うが、その一方であまりにも時代の流れを甘く見ていたようにも感じるのだ。
興味深い歴史の本ではあるものの、その未来を考えたときに、どこか複雑な気持ちになる一冊でもある。