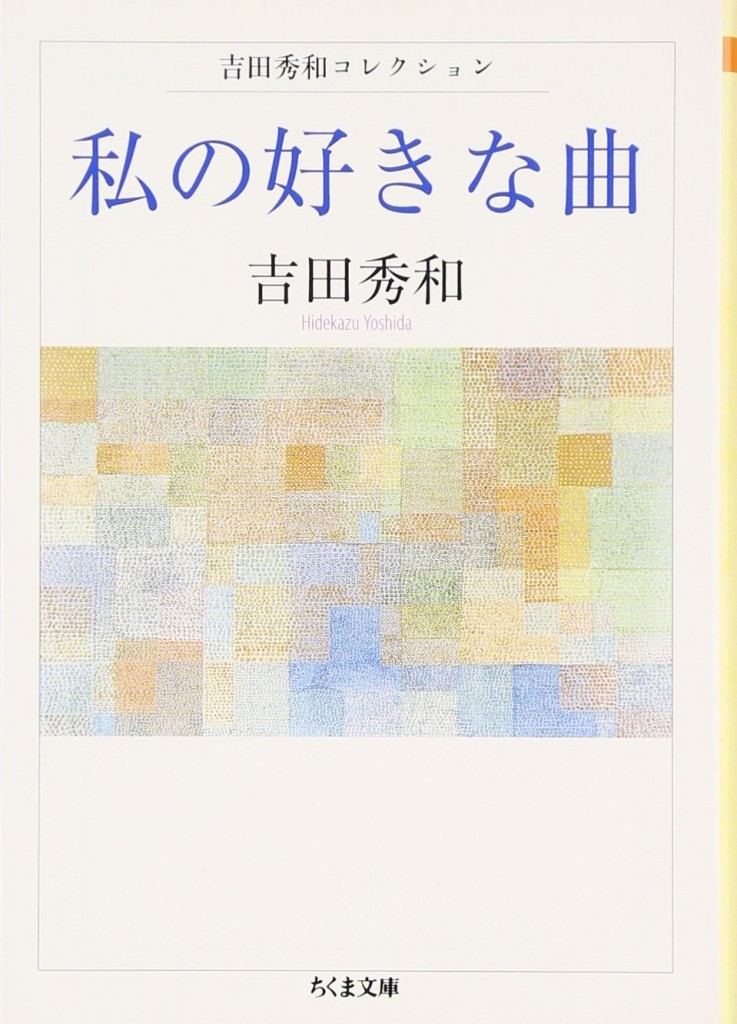 昨年は、あちらこちらの舞台に行って、勘定してみたら64回だった。
昨年は、あちらこちらの舞台に行って、勘定してみたら64回だった。
クラシックのコンサートが一番多く、あとは落語や能、たまに宝塚のミュージカルなどに行く。映画館は一度も行かなかったが、その前年がスターウォーズの1回きりだから、まあそんなものだ。
ただ、何となく興味が変わってきた気もする。音楽だと、オーケストラもいいけど、ピアノソロや室内楽に足を運ぶようになった。オペラは減ったが、能には月2回くらいはコンスタントに通う。
大きな音が億劫になったのかもしれないが、より抽象的なものに惹かれている気もする。殊に能などは、抽象性が高い。
だからだと思うが「難しくないですか?」と聞かれることが多い。たしかに簡単ではないが、じゃあ何が面白くて観に行っているのだろう?と考えてみた。
実は、能の抽象性というのはたしかに「わからない」ところがある。多くは夢幻能という形式だが、そこでは「何らかの霊が降りてきて舞をする」ような展開がある。哀しみとか憂いのようなものはあるのだが、そこであの面だ。実際の表情を見せないことで、想像をしていくことになり、たしかに「わかりやすい」とは思えないだろう。
しかも人の霊ならまだしも、先月観た『遊行柳』などは「柳の精」が舞うのだ。もう、どう考えればいいのか。
いや、しかしそこで理屈を言い出すとつまらなくなる。「柳の精が舞う」という状況は、どう感じようが自由なのだ。
つまり、抽象性が高いほど観る側にとっての自由度は高い。同じ古典でも歌舞伎であればわかりやすい分だ け解釈の余地は少なくなる。
け解釈の余地は少なくなる。
そう考えると、「誰にでも楽しめる」「子供でもわかる」ようなコンテンツは、実は誰にとっても同じように感じることができる分だけ、結構「不自由」なんじゃないかと思う。
ベートーヴェンは多くの作品をつくったが、もっとも世に知られているものの一つは『第九』だろうか。あの曲は3楽章までは素晴らしいと思うが、終楽章になると(少なくても僕には)妙に息苦しくなる感じがする理由もそこにある。
「よろこべ!」と言われたら、もう解釈することなく喜ばなくてはならない。それは、ある意味不自由な体験であり、だからこそ『時計じかけのオレンジ』で使われたのもよくわかる。
だから「抽象的だと難しい」というのは、先入観の問題じゃないかと思う。難しいものは受け手にとっては自由で、やさしいものは実は不自由。わかりやすく、多数が支持するような政策が、後には大きな不自由をもたらしたことだってあるでしょ。
そういえば、先日近所の古本屋で吉田秀和の『之を楽しむ如かず』という評論集を買った。若い時には、音楽を言葉と理屈で修飾しているような感じで敬遠していたが、いま読むと大変おもしろい。
『私の好きな曲』なども読み返すと、「ああ、これが評論だ」と改めて思う。抽象的な音楽を、自由な感性で聴くからこそ評論が独創的な作品として読み継がれる。それは、最近の「音楽ジャーナリスト」には相当難しいことだと思ってしまうし、ツイッターのさえずりでは感想文にすらもならない。
ああ、それにしても書いてることが爺くさくなってきたものだ。まあ、それで楽しいからいいんだけど。
※【追記】そういえば、能というのはなかなかとっつきやすい本がなく、いわゆる入門書みたいなもので「見たい!」という気分にもなりにくいとおもうんだけど、この『異界を旅する能』というのは実におもしろい。一昨年にも書いたけど、能の入門書にして社会評論でもあり、また生き方を考えさせてくれる名著だと思う。








