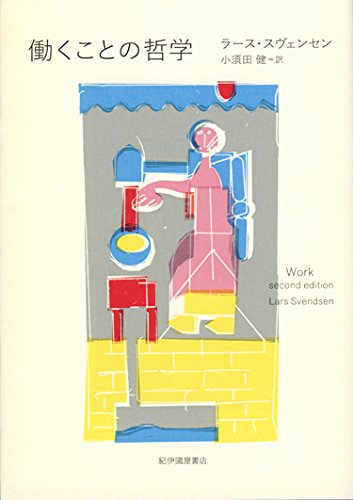 なんども書いてしまうのだけれど、今年を振り返る時に「働きかた」についての話は、とても気になる。ただ「働きかたについての“議論”」というところまで、行っているように思えない。
なんども書いてしまうのだけれど、今年を振り返る時に「働きかた」についての話は、とても気になる。ただ「働きかたについての“議論”」というところまで、行っているように思えない。
時間管理や、副業あるいは在宅勤務などの手法的な問題も大切だろうけど「なぜ、何のために働くのか?」という問いがどこかに行っている。
どれだけ働く環境を整えても、意志と目的を失えば人はいつかは病むかもしれない。それは、すべての働く人にとっての課題だろう。金銭的対価を受け取らないいわゆる「専業主婦」だって同じだと思う。
そして、働き方をめぐる議論は妙な拡散を見せている。
今年は始まって早々に「囲碁とAI」のニュースが大きく報じられた。いままで関心のなかった人の興味を引いたのはいいけれど、案の定「人の仕事がなくなるのか?」という話になだれ込んでいった。
おもしろいことに、そういったことを心配する人ほど、目の前の仕事をきちんとやっていないが、メディアが不安を煽るのには格好の客だったのだろう。
その一方で、「適正な働き方」が問われた。こちらは、十年一日のごとく日本人の長時間労働がテーマである。今日は、電通幹部が書類送検されたようだ。
そういう中で、「働く意味」を正面からとらえた一冊が『働くことの哲学』(ラース・スヴェンソン/紀伊国屋書店)だ。筆者はノルウェーの哲学者だが、書いてある内容はいい意味で「普通の発想」だ。
働くことについて、歴史をさかのぼり考えを巡らせていく。西洋人らしく、ギリシアに始まり、カントを経て、マルクスを俯瞰していくが、思索は平明で説得力がある。
キャリアの根っこを考える上で、最も納得がいった本の1つだ。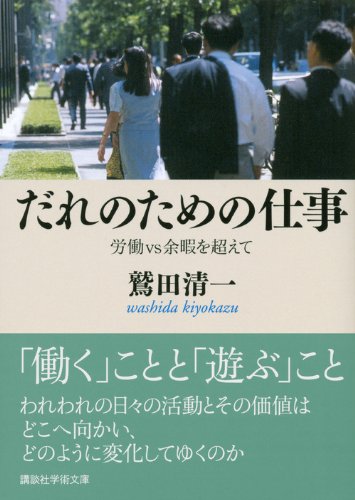
AIと未来についての方は乱立しているけれど、以前にも書いた『人間さまお断り』(ジェリー・カプラン/三省堂)がアタマ1つ抜けて、深みのある思考を感じさせてくれる。
個人的な感じでは、キャリアや働き方の本としては、先の『働くことの哲学』一冊でも大きな収穫だったけ、改めて読みなおしたのが『だれのだめの仕事』(鷲田清一/講談社学術文庫)だ。哲学者であるが、阪大総長まで務めた方だけあって、いい意味で「俗世の感覚」があるのだろう。
1996年の作品に補章があるが、現代の日本を念頭においていて、若い人にも十分読みやすい内容になっている。
来年は「働く意味」を、正面から考えた上で「働き方」が論じられるといいんだけど。








