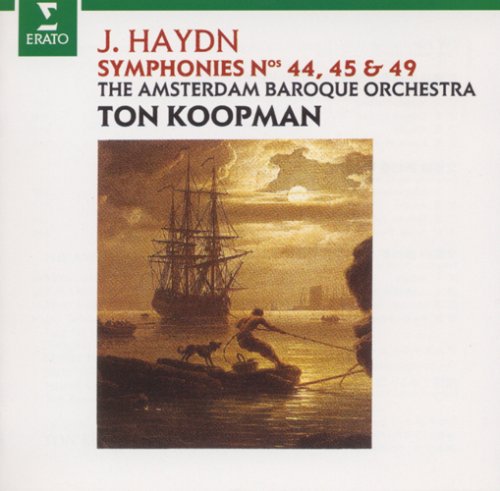104曲も交響曲を書いているし、ドイツ国歌もそうだ。ただバッハほどの崇高さにはおよばず、モーツアルトのような天才イメージも薄く、もちろん時代が下ったベートーヴェンほどに劇的でもない。
しかも、「おもちゃの交響曲」を作ったと言われていたこともあり(実際は違う)、あだ名が「パパ・ハイドン」だ。そして、標題がつくと「軍隊」「時計」に「驚愕」だ。
子ども向けだと「びっくり交響曲」とか言われていたこともあって、イメージ的にも何というか、いま一つ深みがない。
というわけで、若い頃にハイドンのディスクを買ってわざわざ聞こうとはなかなか思わなかった。
そんなハイドンのイメージが変わるのが、短調の交響曲たちだ。なかでも「疾風怒濤期」といわれる時代の曲を集めたこのアルバムは、引き締まった演奏で奥行きも深い。「哀悼」「告別」「受難」という標題がつく3曲だが、最初に聞いた時は、「エ?ハイドンなの?」と思った。
まあハイドンも「やればできる子」的な感じなのだが、また後年の円熟期になるとこうした哀しくも劇的な作風はあまり伺えない。
このディスクの解説(平野昭)は、この辺りの背景についても詳しいのだけれど、それがまた興味深い。ハイドンは30代半ばに宮廷楽団の学長に昇進するのだが、それによって、世俗音楽から教会音楽も受け持つようになった。
そして、教会音楽はバロック様式の影響もあり、短調の増加や激しい感情表出が生まれたという。そして、この時代を「ハイドンのロマン主義的危機(romantic crisis)」と解釈することもあるようだ。また「疾風怒濤」(sturm und drang)という文芸運動は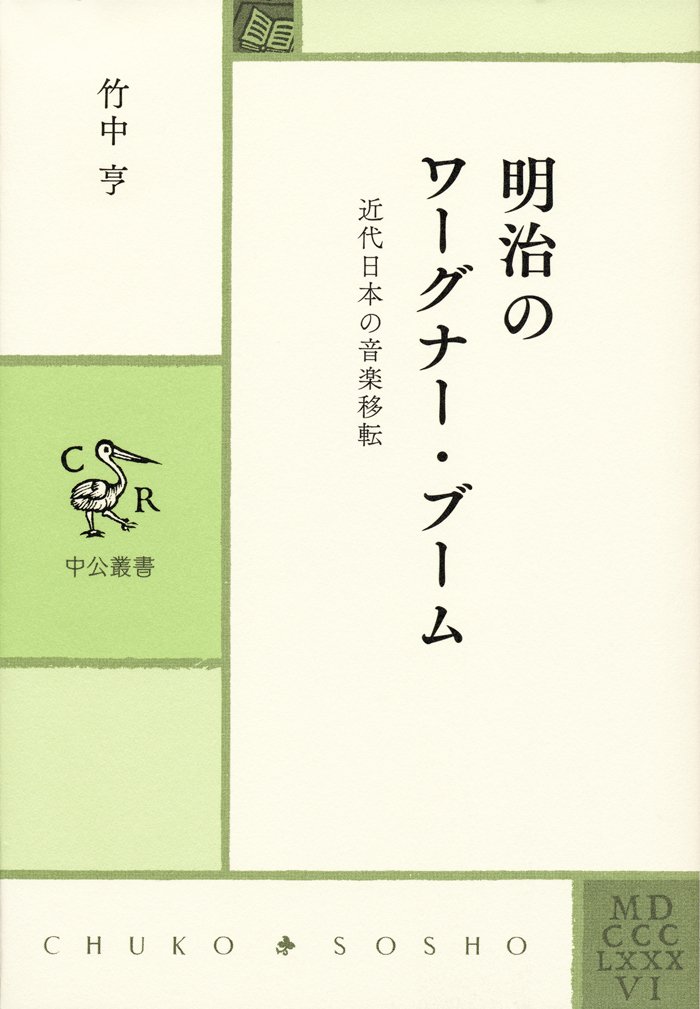 実際にはこれらの曲の後の時期のことだが、何となく連想が働いてそう呼ばれてきたという。
実際にはこれらの曲の後の時期のことだが、何となく連想が働いてそう呼ばれてきたという。
今日は晴れているが、秋雨の多い今秋には妙に聴きたくなる1枚だ。
もっとも、作曲家について、音楽そのものより文字情報先行になってしまうのは、明治以降現在にいたるまでの日本人の宿命なのかもしれない。
耳の疾患に苦しんだベートーヴェンや、病がちで女性関係に揺れるショパンの音楽は「その背景」がイメージしやすく、その情報に沿って音楽も受容されやすい。
一方で、メンデルスゾーンやロッシーニなどはどこか損をしている気もする。
ちなみに「明治のワーグナーブーム」という本は、この辺りの事情を分析しているのだけど、実におもしろかった。
どうして明治時代の日本では、そこまでのワーグナーブームになったのか。そもそも現代でも演奏するのが大変なワーグナーだ。ちゃんと聴いた人はほとんどいないだろうにというツッコミは、昔からみんな気になっていたのだが、そこらをちゃんと検証している。
この日本人の「観念先行」というのは、やたらと欧米の「イノベーション」をありがたがる今の社会とも、どこか似ているのかもしれない。