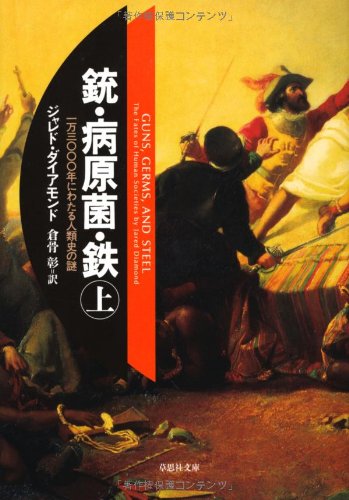 今世紀に入った頃から、世界史の「仕組み」を俯瞰するような本がいろいろと出ているように思う。
今世紀に入った頃から、世界史の「仕組み」を俯瞰するような本がいろいろと出ているように思う。
その理由はいろいろと考えられるが、やはり冷戦の終結は大きいのではないだろうか。社会主義に一定以上の可能性を感じていた時代には、マルクス史観の影響力も大きかった。その呪縛が解けて、もう一度歴史のダイナミズムを研究して、かつ一般読者にもわかりやすく書いた本が、欧米発で生まれている。
一方で、そうした本の中身を若い人に紹介すると、結構興味を持つ人が多い。情報が溢れる中で、「そもそも」の話を知りたい欲求も強いのではないだろうか。
そうした仕組みの観点から、斬新な視点を提示したのはジャレド・ダイヤモンドの『銃・病原菌・鉄』(草思社)だろう。日本版は2000年の発刊だから、ある意味では、定番の本でもある。賛否を含めて、まず一読してみる価値はある。文庫になっていて、kindle版もあるので求めやすいのも魅力だ。
「16世紀にピサロ率いる168人のスペイン部隊が4万人に守られるインカ皇帝を戦闘の末に捕虜にできたのはなぜか?」
そのような、征服と被征服の原因は「銃と軍馬」にあるという。では、その差はどこから生まれてきたのか?
ここで、著者が最も重視するのは地形や生態などの「環境の差」だ。たとえば、食糧生産の伝播は東西には早く伝わるが、南北には遅い。このような差が、長期的には文明の差になっていく過程を解き明かす。
ただし、すべてを環境に帰していくような考え方には、当然異論もある。
産業革命以降の発展の差異に分析の主眼を置いた『国家はなぜ衰退するのか』(早川書房)は、そうしたダイヤモンドの見解とは一線を画す。
『銃・病原菌・鉄』の内容を引用しつつ、批判的に分析しているが、広告には「ジャレド・ダイヤモンド絶賛」とある。世界史の仕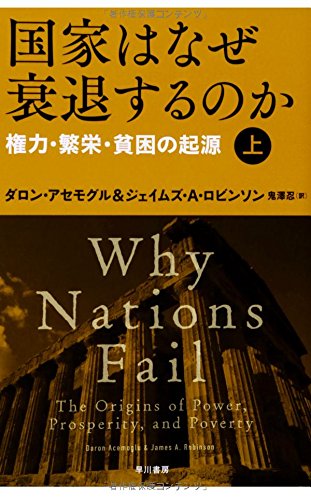 組みが複合的要因から成り立っていることがよくわかる。
組みが複合的要因から成り立っていることがよくわかる。
欧州ではペスト流行後に人口が激減した。そして、英国では労働単価が上昇したが、等々では逆の動きになる。そうした動向が後の市民革命から、産業革命へと展開していく過程を分析しつつ、政治・経済上の制度の差異に「豊かさと貧困」の理由を求めていく。
少々冗長に感じるところが難点で、「銃・病原菌・鉄」に比べると、読み物としてのスリリングな感じではちょっと劣るかもしれない。
ただし、分析の厚みと説得力は大変に高い。
以前に書いた『帳簿の世界史』『水が世界を支配する』のように、一つのテーマに絞って歴史を読み解いた作品と併せて読むのも面白いと思う。








