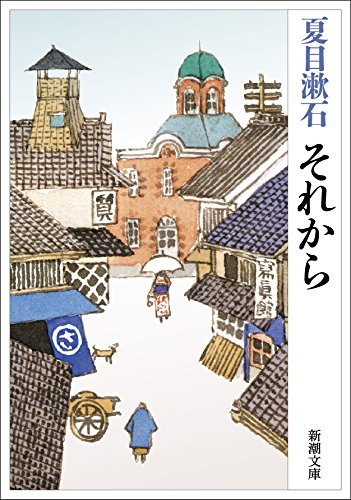 先日読んだジェフリー・ディヴァーの『扇動者』(文藝春秋)は、内容も面白かったのだけど、細かい描写がいかにも現代だった。警察関係者が捜査会議をしている時に、勝手にスマートフォンをいじっている場面が結構出てくる。
先日読んだジェフリー・ディヴァーの『扇動者』(文藝春秋)は、内容も面白かったのだけど、細かい描写がいかにも現代だった。警察関係者が捜査会議をしている時に、勝手にスマートフォンをいじっている場面が結構出てくる。
それが、場の心理を絶妙に表現しつつ、後で考えてみるとちょっとした伏線にもなっているのだが、まあ世界のどこでもスマートフォンはなかなか手放せないだろう。
この小説の場合はスマートフォンの描写がリアリティを高めるのに効果的なのだけれど、現代の人間をそのまんま描写すると、身も蓋もなくなる。ハードボイルドの小説で、探偵がバーカウンターでスマートフォンをいじっているわけにはいかない。
また、古典小説に無理矢理スマートフォンを登場させると、どうなるか。
「クトゥーゾフはくたびれた目でデニーソフをながめはじめ、腹立たしそうな身振りでスマートフォンを見ると、彼の言葉を繰り返した」
「彼が見ていた家から、本当に、デニーソフが話しているあいだに、スマートフォンを片手に将軍が姿を現した」
もう『戦争と平和』の緊張が、どうに緩んでしまう。昔の人から見ると「スマホをいじる人」は、結構間が抜けて見えるかもしれない。
そんな感じで、手持ちの古典小説の頁をランダムに繰っているうちに気づいたのだが、夏目漱石の小説だけは、なんかいかにもスマートフォンが馴染みそうなシーンがあるのだ。
「野々宮君はしばらく池の水を眺めていたが、右の手を隠袋(ポケット)へ入れて何か探し出した。隠袋からスマートフォンが半分はみ出している」
これは、『三四郎』だが、「封筒」をスマートフォンに置き換えてみた。なんか、馴染む。
「なんだかべらべら然たる着物へ縮緬の帯をだらしなく巻きつけて、例のとおりスマホをぶらつかせている。あのスマホは偽物である」
こちらは『坊っちゃん』で、「金鎖」をスマホを置き換えた。金鎖をぶらつかせているのは、ご存知赤シャツだ。
「三千代は何も答えずに室の中に這入て来た。セルの単衣の下に襦袢を重ねて、手に大画面のスマホを持っていた。そのスマホをいきなり洋卓の上に投げるように置いて、その横にある椅子へ腰を卸した」
これは『それから』の一節で、「大きな白い百合の花」をスマホにしたんだけど、なんか妙にしっくりくる。
つまり、漱石の描写は具体的で映像が浮かびやすく、その時代の小道具を巧みに配しているということなんだろう。漱石が現代においても読み継がれていて、かつ古典の中では読みやすさを感じるのは、こうしたことも理由かもしれない。
ちなみに、彼の小説でもっともスマホにはまりそうなのは『それから』の代助のような気がする。
なんか日がな一日、ダラダラとスマホをいじっては退屈そうにしながら、ふらりと街に出ていくような感じで、なんか今だって本当にいそうなんだよな。
※ちなみにkindleだと、ほとんどの作品を読める「漱石大全」というのがあって、年代順に整理されている。他の作家も含めて、旅先で気が向いた時に読めるから重宝している。








