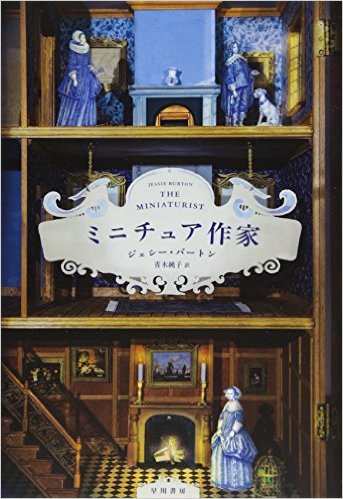 [読んだ本]ジェシー・バートン著 青木純子(訳)『ミニチュア作家』(早川書房)
[読んだ本]ジェシー・バートン著 青木純子(訳)『ミニチュア作家』(早川書房)
もう夏も終わるかのような陽気で、かつ世界経済大荒れ感の中で、もうちょっと現実離れした欧州の時代小説を二つほど。
まずは、『ミニチュア作家』という17世紀のオランダを舞台にした作品。著者は1982年生まれの英国の女優だが、経歴には「舞台に立つかたわら、シティで秘書として働く」とあるから、まあ売れっ子というわけではないのだろう。ところがこの作品は欧州では相当受けたようで、昨年出版されて32ヵ国で翻訳出版されて、英国の書店チェーンの「ブック・オブ・ザ・イヤー」受賞というのは、ちょうど「本屋大賞」といった感じだろうか。
アムステルダムの裕福な商人の家に嫁いだ18歳の娘を取り巻くちょっとミステリアスなストーリー。夫、義妹、使用人など皆が秘密を抱えているような空気の中で、物語はそのヴェールを一枚ずつはがしていくように進んでいく。
夫からの贈り物である、素晴らしいドールハウスと、それを「作っているらしい」ミニチュア作家の存在がストーリーの通底で謎めいた雰囲気を醸し出している。ただし、ミステリーというよりは、ファンタジー的な要素も色濃いため、あまりカッチリしたお話と期待してしまうと、肩透かしを食うかもしれない。
夫はオランダ東インド会社の一員という設定で、この時代のビジネスの雰囲気が伝わってくるのも面白い。レンブラントの絵を思い浮かべながら読むといいんじゃないかな。
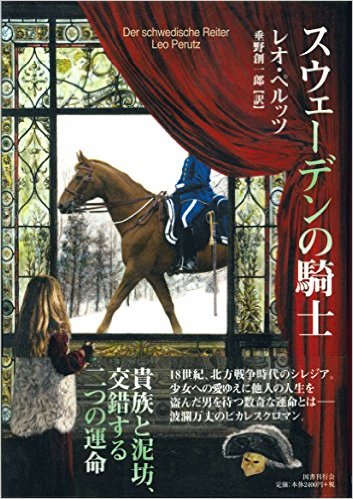 [読んだ本]レオ・ペルッツ著 垂野 創一郎(訳)『スウェーデンの騎士』(国書刊行会)
[読んだ本]レオ・ペルッツ著 垂野 創一郎(訳)『スウェーデンの騎士』(国書刊行会)
そして、こちらは1701年の中欧が舞台の小説なんだけど、『ミニチュア作家』よりも30年以上後の時代とは、まったく思えない。100年前の話といってもいいくらいで、それが当時の欧州だったのだろう。
裕福な都市国家であるアムステルダムと、北方戦争で荒廃した内陸部。こちらの主人公は、騎士と泥棒だ。寒さと飢え、そして生き残りを賭けた駆け引き。没落した貴族と、狡猾な盗賊団、出てくるキャラクターは「悪禍男爵」「首曲り」「赤毛のリーザ」に、煉獄帰りの粉屋と個性がギラつき、まあRPGのような仕立てになっている。
とはいっても、この作品は1936年つまり2つの大戦間に書かれた作品なのだ。現代のゲームの方が影響を受けたのかもしれない。作者のペルッツの作品は、今世紀になってから日本語訳が出るようになってきた。伝奇小説といってもいいかもしれないが、ファンタジーのように読ませながら、最後にはきっちりと着地していて、そこに妙なリアリティを感じる。
リアルに描いているようで、どこか霧の中のような『ミニチュア作家』とは対照的で、読み終わったあとに、もう一度読み返してみたくなるようなところがある。
この夏は、「プロ倫」を中心に回る惑星をたどったような読書だった。宗教革命の後の欧州は、まさに「カネとチカラ」を原理とした譜面に描かれた大芝居なのだということが感じられる。戦後70年を考えるなら、400年くらい遡らないとわからないことも多い。
この2冊には欧州の小説のズッシリとした底力がある。理論の本は骨格だけど、小説という肉付きがあって、歴史は面白くなるんだよなと痛感した。








